六人の噓つきな大学生
基本情報
| 著者 | 浅倉秋成 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2023/6/13 |
あらすじ
成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用。最終選考に残った六人の就活生に与えられた課題は、一カ月後までにチームを作り上げ、ディスカッションをするというものだった。全員で内定を得るため、波多野祥吾は五人の学生と交流を深めていくが、本番直前に課題の変更が通達される。それは、「六人の中から一人の内定者を決める」こと。仲間だったはずの六人は、ひとつの席を奪い合うライバルになった。内定を賭けた議論が進む中、六通の封筒が発見される。個人名が書かれた封筒を空けると「●●は人殺し」だという告発文が入っていた。彼ら六人の嘘と罪とは。そして「犯人」の目的とは――。
Amazon 紹介文より引用
感想【ネタバレ注意】
いやぁ~、面白かった。前から読んでみようと思っていた「六人の嘘つきな大学生」を読みました。
読み終えたときは鳥肌が立ちました。ミステリーだと思って読んでいたものが、実は人の無意識を描いたものでした。
この小説は就活生時代の「就職試験」と、数年経った後の「それから」に分かれています。
あらすじから分かるように、就職試験では6人の知られたくない過去が暴かれていきます。登場人物たちと同じように読者である私も、「この人、こんな人だったの!」とショックを受けました。
前半の六人での仲の良い様子を知っているから告発されていくときの裏切られた感は半端なかったです。それを強固にしたのが「就職試験」の文中に入る登場人物らの回顧録でした。告発文と回顧録によって、読者の私には登場人物はそれぞれ「こういう人たちだ」という思い込みが生じました。
そのため「それから」で当時のインタビューを読んだときには衝撃でした。
同じ人、同じ行動を見ていても、見る人によっては捉え方が変わるし、見る人が同じでもタイミングやもっている情報量で捉え方は変わる。その冷静に考えれば当たり前なことも、実際にそのことを念頭に置いて人と接することができるかといわれると難しい。
人はひとつの側面から見ただけでは理解できない。この当たり前が、前半の刷り込みの上手さによって私の頭から完全に忘れ去られていました。登場人物たちも就職試験に加えて告発文という非日常のオンパレードの中で人を多角的に見ることができなくなっていたのでしょう。
この、人は多面的であり一つの視点からはその人の全体は決して見えないという当たり前だが見落としてしまいがちな、人間の無意識の恐ろしさを感じた小説でした。
人は限りなく球体に近い多面体
「人は二面性をもつ」といいます。しかし、実際にはもっと多くの面をもっています。家族の前での私、友人の前での私、学校での私、バイト先での私、これらはすべて私だが同じ面を見せているかと言われればそうではないです。喋り方や表情、冗談などの距離感などいろいろと異なります。
人は数えきれないほど多くの面をもっていて、その面が多くなればどんどん球体に近づいていく。ひとつの視点からでは球体の全体を見ることができないように、人もひとつの視点からは判断できない。この小説を読んで、私はそう考えるようになりました。
また、誰と一緒にいるかという違いだけが人間の多面性ではありません。
同じ人の同じ行動を見ても、人によってその捉え方は変わってくる。その時どのような情報をもっているかによっても変わってくる。
「六人の噓つきな大学生」では、就職試験で隠し通そうとしていた秘密が告発という形で暴かれました。たしかに、その秘密は告発されるまで読者も他の5人の就活生も知らなかったため、告発されたときにはその人の全く異なる一面を見たと感じました。
しかし「それから」を読めば分かるように、告発内容も見る角度によっては理解しがたい犯罪に近いものにもなり、また別の角度から見たら正当性のある行動にも思えてきます。
同じものでもどこから見るか、何を通して見るかで捉え方は異なるのです。
まとめ
人には多面性があり一度にすべての面を見ることはできないし、一生かかってもすべてを知ることはできません。
自分も相手も限りなく球体に近い多面体であるならば、お互いが理解できるのはその二つの重なり合った部分だけです。
だから、人と接するときは相手はこんな人だと決めつけることはせず、相手の一部と自分の一部で関わり合っているだけで、お互いにお互いの知らないところをもっており、それらは知らなくて良いものであると考えられるようになりました。
それに気づくことができた小説でした。

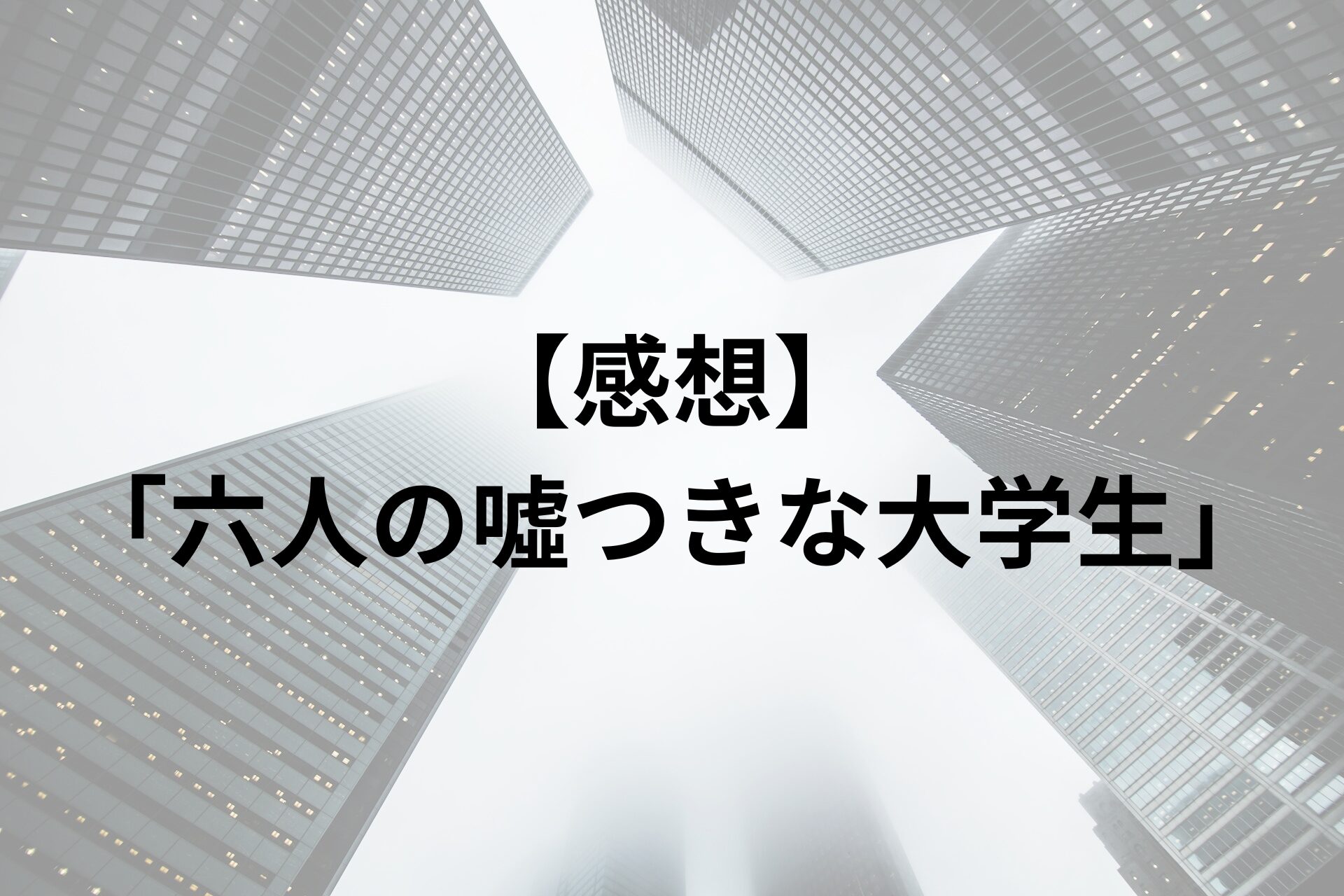
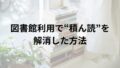
コメント